目次
はじめに
いつもご愛読ありがとうございます。咲くキャリ情報局です。今回の記事では、「ブロックチェーン入門」について詳しく考察していきたいと思います。具体的には、
1.ブロックチェーンの定義
2.ブロックチェーンの仕組み
3.ブロックチェーンのメリット
4.ブロックチェーンのデメリット
5.ブロックチェーンの種類
6.ブロックチェーンの具体例
以上の章立てで見ていきたいと思います。最後までお付き合いいただければ幸いです。
1.ブロックチェーンの定義

ブロックチェーン(Blockchain)とは、「サトシ・ナカモト」氏が発明した、一連の取引情報を束ねているデータの塊であるブロックを、鎖の様に連続してつなげていく技術のことです。
ブロックチェーンを活用すると、改ざんできない形で、検知情報や金銭的価値を記録して保存ができます。元々はビットコインに使用されている技術ですが、近年では後の章で触れますが、多種多様な業界で活用されています。ブロックチェーンでは、各ブロックでデータを保存するため、データの偽造や改ざんが極めて困難になるというのが最大の特徴です。ですので、この技術の最大の特徴は、情報が分散して保存されるため、中央集権的な管理が不要となる点です。このように中央集権的な組織が介入できず、公正に取引を記録できるのがブロックチェーン技術の特徴であると言えます。
少し難解な表現も含まれますが、日本ブロックチェーン協会によるブロックチェーンの定義もご紹介させていただきます。
①ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを用い、時間の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプロトコル、またはその実装をブロックチェーンと呼ぶ。
②電子署名とハッシュポインタを使用し改竄検出が容易なデータ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデータ同一性等を実現する技術を広義のブロックチェーンと呼ぶ。
以上がブロックチェーンの定義となります。
参考出典:
2.ブロックチェーンの仕組み
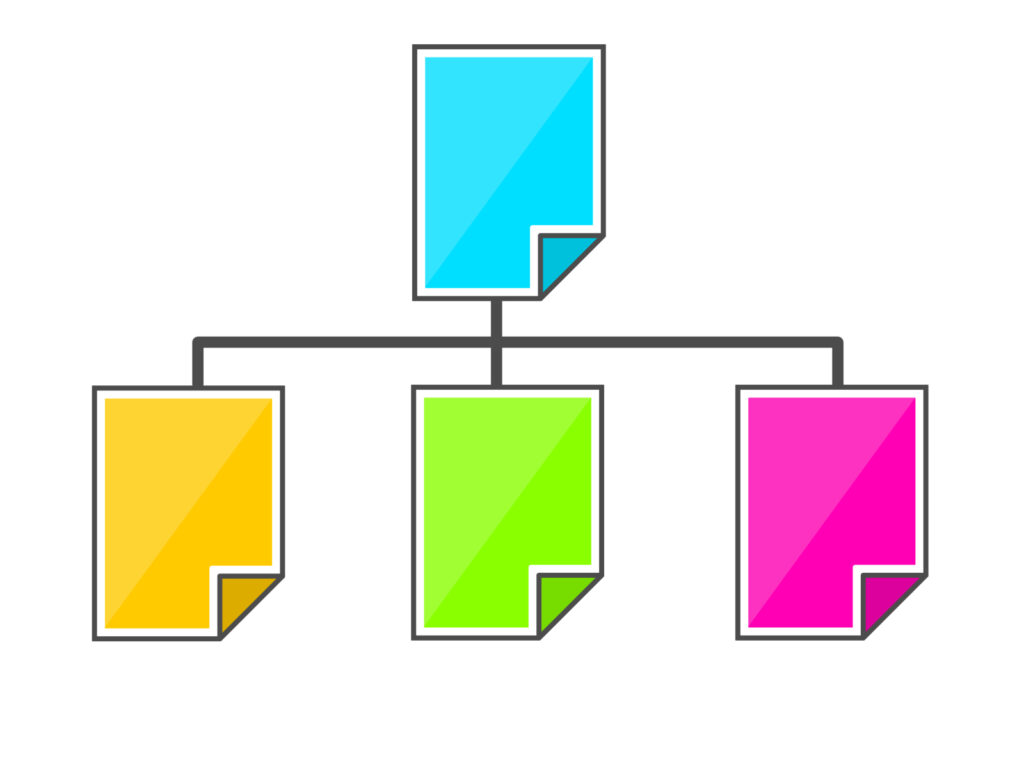
・スマートコントラクト
スマートコントラクトとは、「あらかじめ決めてある条件」をクリアした場合に、自動的に取引(transaction:トランザクション)が実行される仕組みのことです。このスマートコントラクトが実現すると、プログラムの自動化、コスト削減、透明性のある取引のため信頼できる等の利点があります。
・分散型台帳
分散型台帳とは、データを中央サーバー1か所に集中させるのではなく、ノード(ネットワーク上の複数のコンピュータやデバイス)上に分散して保存するという技術のことです。これにより、各参加者が同じ取引データを持つことになります。つまり、情報の改ざんが困難になるため、取引の安全性と透明性が高まります。ですので、信頼性が高い取引を行うことができます。
・ハッシュ(hash)
ハッシュとは、元のデータから計算された規則性のない値で、データの特定に長けた暗号化技術のことを指します。もし元データから少しでも改ざんされていたら、「ハッシュ関数」と呼ばれる計算式を通すことで、全く違うハッシュ値となります。このハッシュ値はIDになるので、正しいハッシュ値と比較することで、即座にデータの破損や改ざんを発見できます。ハッシュ自体は簡単に生成できますが、ハッシュを用いて元のデータファイルを復元するのはものすごく大変な作業になります。この様な特徴があることから、ハッシュは暗号技術としてよく活用されます。
・コンセンサスアルゴリズム
コンセンサスアルゴリズムとは、不特定多数の参加者の間で合意(コンセンサス)を得るための仕組みのことです。取引の正当性を確認するために、不特定多数の参加者(ノード)がいるブロックチェーンのネットワーク内で合意形成が行われます。これこそが、コンセンサスアルゴリズムの重要な役割だと言えます。この様に、コンセンサスアルゴリズムの厳しいルールがあるので、ブロックチェーンは分散型台帳でありながら、一貫性を保つことができます。すなわち、正常に動作しない者や取引時に不正を働く者が含まれていても、正しく合意(コンセンサス)を形成できるのです。
代表的なアルゴリズムには、Proof of Stake(PoS)やProof of Work(PoW)があります。
・暗号技術
ブロックチェーンのブロックごとに、取引情報をハッシュ関数や公開鍵暗号を使用して暗号化しています。ちなみに、ハッシュ関数はブロックの内容が1文字でも変更されると全く違うものが生成されるため、データの改ざんが即座に発見できます。この暗号化技術によりデータの安全性が確保され、内容の秘匿性が高まり、悪意ある攻撃に対するセキュリティが向上します。
・P2Pネットワーク
P2P(Peer to Peer)とは、参加者のコンピュータが、対等な権限で直接接続するネットワークの接続方式のことです。これにより、システムが分散されており、一部のコンピュータがダウンしたとしても、全体のシステムはダウンしない分散システムを実現することができます。つまり、中央管理サーバーがないため、通信の自由度が高く、また障害に対して高いレベルのセキュリティを保つことができます。
・マイニング
マイニングとは、データをブロックチェーンに保存する作業のことです。具体的に言うと、参加者(マイナー)が暗号資産の取引データを不正がないかを検証・確認し、その記録をブロックチェーンに記録していく作業を指します。この過程で、参加者(マイナー)は、作業の対価として取引の承認を得たり、仮想通貨を獲得できます。また、マイニングを行うとネットワークの安全性を保つことができます。
・電子署名
電子署名とは、「公開鍵」と「秘密鍵」で作成されるもので、デジタル文書の作成者を証明する電子的な署名のことです。電子署名者は「秘密鍵」を使ってデータの署名をして受信者に送ります。電子署名の受信者は事前に送られてきている「公開鍵」を使うことで、データを電子署名者が作成したものであると確認できます。この一連の作業を経て、データの改ざんや「なりすまし」を防止しています。2001年4月1日に「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令」という法律も施行されました。
参考出典:
3.ブロックチェーンのメリット
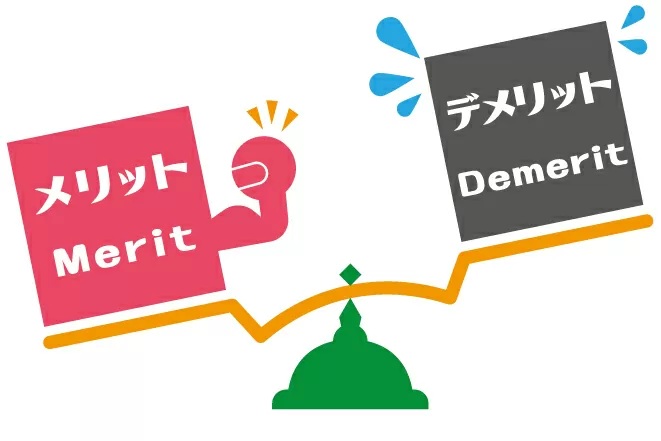
・24時間稼働
ブロックチェーンシステムにおいては、24時間稼働しているので、夜間におけるリアルタイムのお金の振り込みや決済も可能です。これにより、自動販売機の決済や無人店舗などの商売が可能になります。
また、ブロックチェーンをビジネスインフラとして活用する場合、分散台帳型システムのため定期的なメンテナンス時にサービスを停止する必要が無くなります。またサイバー攻撃にあっても、分散台帳型システムのため、サービスを停止せずに、局所的な障害にも対応できます。さらには災害時にも分散型台帳システムのため、故障している箇所を避けてサービスを継続できます。
・公明な記録を残すことができる
ブロックチェーンシステム下では、中央集権的な管理者を廃止しています。これにより、たとえサービス提供者でも 取引の記録の消去や改ざんを行うことができません。この性質により、ブロックチェーンは、例えば年金支払い、不動産登記、納税などの公的分野での記録にも役立ちます。
ブロックチェーンでは、参加者全員の合意に基づき取引記録の正当性が検証されるため、格納されているデータに高い公正性が担保されています。この仕組みでは、参加者全員が記録内容を評価し、大多数の合意をもって正当性を判断する、いわゆるコンセンサスアルゴリズムが用いられています。
・セキュリティ水準が高い
ブロックチェーンでは、データを保護するために、暗号化と分散技術を活用しているので、サイバー攻撃を防御でき、さらには、データ改ざんやハッキングや非常に困難にすることが可能です。ここで言う暗号技術とは、取引情報のデジタル署名、公開鍵暗号方式による参加者の認証、ハッシュ値による履歴保護などのことです。
ブロックチェーンでは、全参加者のブロックごとに、全データが分散して格納されているため、万が一、サイバー攻撃にあっても一部が使えなくなるだけで、システム全体の安全は保たれます。いわゆるZDT((ゼロダウンタイム)システムが壊れる前に知らせる仕組み)も導入されています。また、コンセンサスアルゴリズムにおけるルールも改ざんを防ぐ仕組みの1つであると言えるでしょう。これらの仕組みにより、企業や金融機関はブロックチェーンを安心して活用できるのです。
参考出典:
4.ブロックチェーンのデメリット
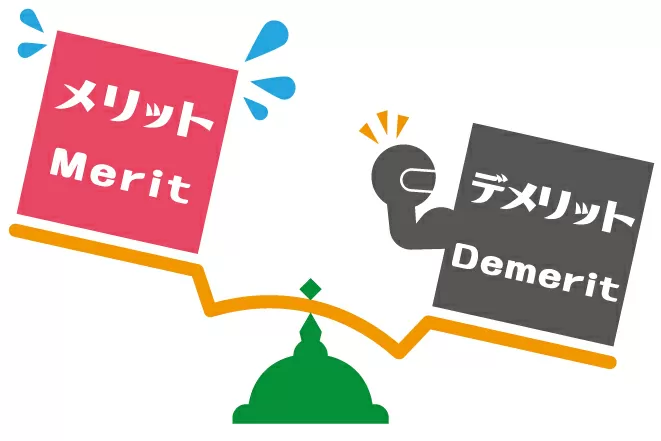
・合意形成(決済完了)に時間がかかります。
現在のクレジットカード決済では決済時間は一瞬で済みます。この決済システムをブロックチェーンで運用する場合、合意形成(決済完了)までに時間を要します。ですので、世界的な決済手段として実用されるまでには、まだまだ改善が必要だと言えるでしょう。これは、現時点ではデメリットだと言えるでしょう。
・スケーラビリティの問題があります。
まず、スケーラビリティ(システムやアプリケーションなどが、利用者数や処理量の増加に柔軟に対応する能力)の問題があります。ブロックチェーンネットワーク上の取引量が増えると、ネットワークが混雑して、処理速度が低下し、取引が遅延する可能性があります。この現象を解消するために、全ての参加者がすべての取引履歴を持つ方式を改良して、参加者を分散化して運用していく、つまり運用負荷を減らしていく工夫も求められています。また、ブロックチェーン技術では、信頼性の確保や処理能力を上げていくために、今まで以上に技術革新が求められています。
・大量のエネルギー消費の問題があります。
特に、ブロックチェーンでは、プルーフ・オブ・ワーク(PoW、膨大な計算量を必要とする作業を成功させた人が取引の承認者となり、新たなブロックをブロックチェーンに繋ぐ権利を得られる仕組みのこと※1)を採用しています。プルーフ・オブ・ワークでは、コンピュータを動かすのに膨大なパワーを要するため、大量の電力を消費しています。特にビットコインのマイニングでは、年間で国家レベルの電力を消費しているそうです。これに対して、SDGsの実現に向けて、グリーンマイニング(環境負荷の低いマイニング)を研究する動きが高まっています。この、グリーンマイニングが実現すれば、大量電力消費による大量のCO2の排出を減らすことができます。
・法的な規制や標準化の問題があります。
仮想通貨を悪用してマネーロンダリングを行う事例が後を絶ちません。そのため、マネーロンダリング対策の面から規制強化が検討されています。しかしながら、各国でブロックチェーンに対する法律が異なるので、なかなか規制強化が難しいという現実もあります。その一方で、ブロックチェーンのイノベーションが各国の法律が違うことで阻害される恐れもあるので、規制する国家当局の対応には慎重にしつつ、各企業は法令順守で事業計画を立てなければいけません。
・データを消せないですし、隠せません。
ブロックチェーンのネットワーク上で、個人情報を取り扱う場合、各ブロックに個人情報が暗号化された形で格納され、全ての参加者に情報がいきわたるので、データを隠すことが出来ません。また、一度個人情報が記録されると、暗号化された個人情報が2度と削除されません。これらを防ぐためには、ブロックチェーンだけではなく、個人情報を安心して格納できる外部のデータベースなどと組み合わせて使う必要があります。
・導入コストが高いです。
決済サービスにブロックチェーンを活用する場合、初期費用としてスマートコントラクトや分散型台帳、暗号化通信等の仕組みの構築に、多額の初期投資が必要になります。さらには、仮想通貨に必要なマイニングには多額の電力を要するので、電気代も膨大にかかります。
これらの初期費用などを回収するには、決済サービス料金や、マイニングの取引手数料や、マイニングでできたコインなどで回収していくほかありません。このように初期投資には多額の出費が必要ですが、規模の経済から考えると一定規模以上では低コストでの運用が可能になるので、拡張性のメリットをきちんと考えながら導入するかどうか、決めた方がよさそうです。
・実装に技術力が必要です。
ブロックチェーンの運用・保守には高いスキルが求められます。たとえば、分散型台帳のシステム、マイニング、暗号化通信、高水準のセキュリティの確保、グローバルなネットワークとの共存、といった専門的知識が必要になります。
これらの先端技術を習得している人材の採用や、こういったエンジニアを育成するコストが必要といった面からも、ブロックチェーン導入には十分な検討が必要だと言えるでしょう。
参考出典:
※1はICHIZEN CAPITALより引用
5.ブロックチェーンの種類

・コンソーシアムブロックチェーン
コンソーシアムブロックチェーンは、コンソーシアム(合弁ではない2つ以上の個人、企業、団体、政府、あるいはこれらの任意の組合せから成る団体※2)によって共同管理される、許可が必要なブロックチェーン技術のことです。技術的には、プライベートブロックチェーンとパブリックブロックチェーンの中間の技術で、取引や参加者が限定されますが、効率的なシステムで高水準のセキュリティを保つことができます。また、事前に認められた参加者だけが、データや取引記録を確認することができます。これらの特徴により、改ざんや不正アクセスのリスクを低くすることが可能になります。すなわち、機密情報の保護が可能になります。さらには、コンソーシアムで形成しているブロックチェーンのため、トランザクション処理速度が速く、合意形成プロセスも迅速なため、スケーラビリティにも優れています。
・プライベートブロックチェーン
プライベートブロックチェーンとは、管理者の承認を得た、参加者(特定の組織やグループ)のみがアクセスできる閉じられたネットワークのことです。管理者である中央集権的な組織により制御されるため、取引記録は許可された参加者のみが見ることができます。これにより、高水準のプライバシーやセキュリティを保つことができます。また、参加者の権限が制限されているため、トランザクションの処理速度が速く、スケーラビリティに優れている点が挙げられます。参加者を承認制で決めているため、参加者の総数管理や、悪意を持つ参加者が含まれるリスクを抑えやすいことから、厳格なコンセンサスアルゴリズムがなくとも機能できるシステムです。そのため、スピーディな取引が実現できます。一方、デメリットとしては、中央集権的な管理者を必要とするため、ネットワークの分散性が低いことが挙げられます。
・パブリックブロックチェーン
パブリックブロックチェーンは、オープンで誰でもアクセス・参加できるネットワークのことです。参加者は自由に取引を行うことができます。全ての取引が公開されているため、参加者ならば確認でき、また新しいブロックを追加するためのマイニングも行えることが特徴です。データは暗号技術で保護した上で、分散管理を行うことでセキュリティを高水準で保つことができます。代表な例としては、イーサリアムやビットコイン(Bitcoin)が有名です。ただし、パブリックチェーンは誰がいつ参加しても脱退しても良いため、参加者の総数を把握することはできません。参加者の中には正確に動作しない方や、不正を働く方も存在するので、この前提を踏まえたうえで運用していく必要性があります。
・パーミッションドブロックチェーン
パーミッションドブロックチェーンは、参加者は事前に承認されたメンバーのみがアクセスできる許可型ブロックチェーンです。承認されたメンバーだけがネットワークに参加ができるため、外部からのデータ改ざんや不正アクセスのリスクが低くなるというメリットがあります。これにより、効率的な処理能力が高いため、高水準のプライバシー保護、高水準のセキュリティを実現できます。また、承認されたメンバーのみで合意形成をするため、トランザクション処理速度が速く、スケーラビリティにも優れています。このような特徴から、ビジネスニーズごとにカスタマイズが可能なため、サプライチェーン管理、医療、金融などの分野での有効活用が期待されています。ただし、デメリットとしては、中央管理者が必要なので、ネットワークの分散性が低いことが挙げられます。
・ハイブリットブロックチェーン
ハイブリッドブロックチェーンは、プライベートブロックチェーンとパブリックブロックチェーンを組み合わせたものです。プライベートブロックチェーンのセキュリティとパブリックブロックチェーンの透明性を兼ね備えているので、必要な部分を公開しながら、機密情報を保護することができます。このように、一部のデータを公開し、一部を非公開にできるのが最大の特徴です。柔軟性と適応性を兼ね備えているので、ビジネスにおけるニーズに柔軟に対応することができます。ただし、プライベートとパブリックとの特性を適切に組み合わせるために、高度なレベルの技術者が必要になります。
参考出典:
※2はWikipediaより引用
6.ブロックチェーンの具体的活用例
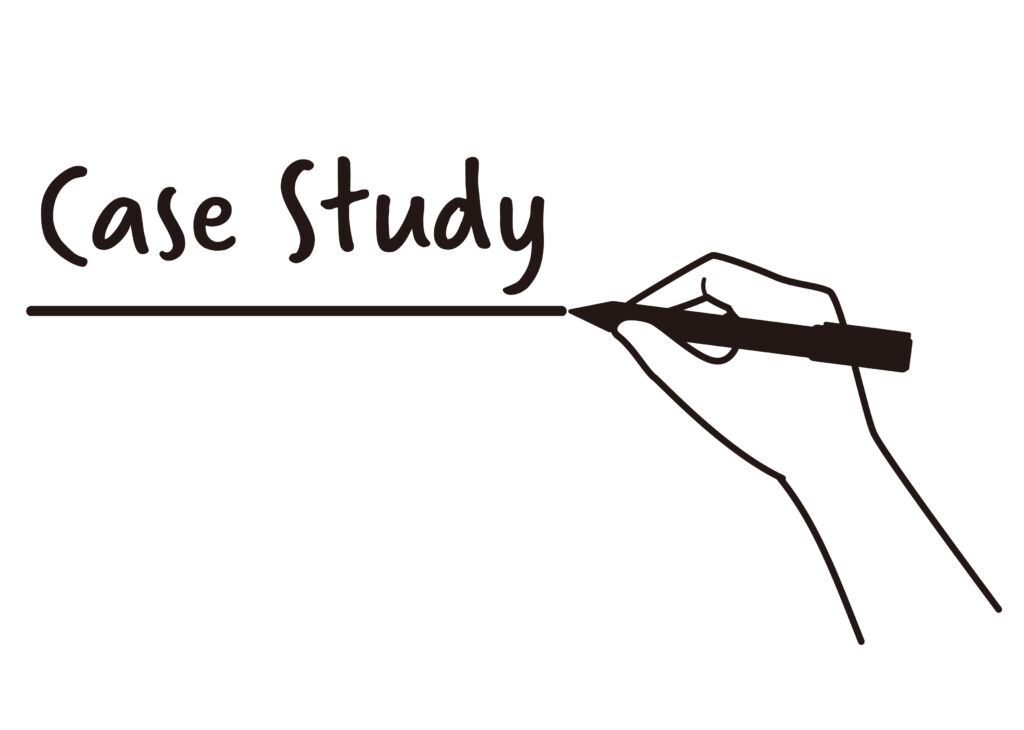
・SCM(サプライチェーンマネジメント)
SCM(サプライチェーンマネジメント)とは、サプライチェーンを管理し、原材料の調達から製品の製造、流通、販売、そして消費者への提供までのプロセスを、最適化・効率化して管理する経営手法※3のことです。このSCMにブロックチェーン技術を用いることで、製品の製造から消費者への提供までのプロセスをリアルタイムで追跡できます。これにより、製品のトレーサビリティが向上し、B級品や偽造品を排除できるので、消費者は安心して商品を購入できるようになります。
・仮想通貨の取引基盤
ブロックチェーン技術が最も活用されているのは、仮想通貨の取引基盤です。具体的には、取引データを暗号化し、ブロックに格納する技術のことです。ブロックチェーン技術では、ハッシュ関数と公開鍵暗号方式とを使用することで高水準のセキュリティを実現しています。これにより、不正アクセスや改ざんが極めて困難になります。
仮想通貨の取引は、中央集権的な銀行や証券会社を通さずに、このブロックチェーン上で行われ、送金人から受取人への送金したデジタル通貨が記録されます。
・デジタルアイデンティティ
デジタルアイデンティティとは、オンライン上における個人を証明する個人情報の集まりを意味します。現実世界では運転免許証、健康保険証、パスポートなどを使用して本人確認が行われます。これと同様に、オンライン上ではブロックチェーン技術を用いて個人や組織を識別し、オンラインで本人確認の正当性を確認することが可能になります。また、ブロックチェーン技術を用いているので、プライバシーの保護が強化され、高い水準でセキュリティが保たれています。
・不動産業界
不動産売買において、地面師などによる詐欺被害を防ぐために、ブロックチェーン技術が用いられています。この詐欺とは二重譲渡や不正のことです。これを防ぐために、ブロックチェーン技術を用いて、契約の履行や所有権の証明を行います。
・マーケットプレイス
オークションサイトやフリーマーケットサイトで個人同士が売買を成立させるために、ブロックチェーン技術を活用することが増えています。代表的な例はアメリカのOpenBazaarです。ブロックチェーン技術により、出品者と購入者がサイト上で直接取引を行う際に、匿名性を担保し安全な取引を確立しています。さらにすごいのは、サービス利用のための手数料がかからない点です。また、OpenBazaarでは、決済にビットコインを採用しています。
・行政サービス
ブロックチェーン技術を行政サービスに活用している代表的な事例は、公益財団法人 東京市町村自治調査会の調査によると下記の通り※4です。
①福岡県飯塚市・・・住民票等各種証明書のデジタル化
②熊本県熊本市・・・行政文書を安全かつ透明性の高い情報として公開
③佐賀県佐賀市・・・ごみ発電電力の地産地消による環境価値を電子証書化
④石川県加賀市・・・マイナンバーカードとブロックチェーンを活用した行政サービスの提供
⑤福島県磐梯町・・・地域商品券をスマホアプリによって発行
・クロスボーダーペイメント
クロスボーダーペイメントとは、国境を越えて行われる支払人と受取人が異なる国にいる金融取引のことです。この様な国をまたいだ送金では、決済処理に長時間の時間を取られ、なおかつ高い手数料がかかっていました。しかし、ブロックチェーン技術が発明されたことで、送金コストが大幅に削減され、また、高水準のセキュリティのもとでのリアルタイム送金が可能になりました。
参考出典:
※3はSAPより引用
※4は公益財団法人 東京市町村自治調査会より引用
まとめ
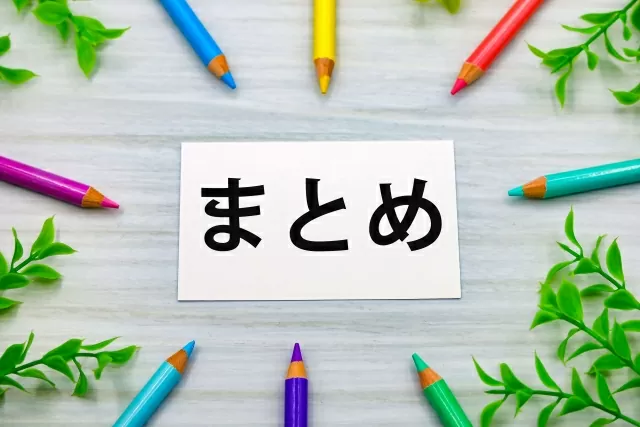
今回の記事では、「ブロックチェーン入門」について詳しく考察してきました。具体的には、
1.ブロックチェーンの定義
2.ブロックチェーンの仕組み
3.ブロックチェーンのメリット
4.ブロックチェーンのデメリット
5.ブロックチェーンの種類
6.ブロックチェーンの具体例
の章立てで見てきました。
ブロックチェーン技術は軌道に乗ってしまえばコスト安ですが、初期投資が高いので、投資した場合に元が取れるかを、きちんと見極めた上で採用するかどうかを決定する方が良いと言えるでしょう。
今回も最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
参考出典:

